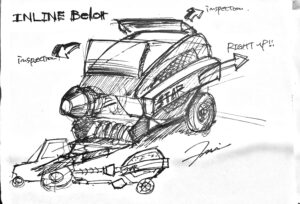色々な場に出て行くと、さまざまな企業の方々にお目にかかり、クリエイティブエンジニアリングの話をさせていただく機会が沢山あります。
全く興味のない方々もいらっしゃいますが、興味のある方々は、もっと話を聞かせて欲しい!今度伺います!会社に来てください!となり、実際伺ってより詳しいクリエイティブエンジニアリングの話と、面会企業に適したクリエイティブエンジニアリング活用方法を時系列で説明したりします。
そこで終わってしまう企業さんもいらっしゃいますが、それを進めて行くには、どのくらいの費用がかかりますか?1年で成果を出したいが、期間を詰めて行うことはできるのか?
と問われます。
ここから、デザインフィーが大きな影響を与える折衝ごとになるのですが、クリエイティブエンジニアリングはデザインと技術を並行に進めて行く手法です。
拡大解釈すれば「社会が必要であろう製品、サービスと企業の強みを天秤にかけつつ、整合して行く」ような感覚で、デザインと技術を行ったり来たりします。
よって、デザイナーだけではできないため、あらゆるブレーン企業に協力してもらいながら行います。また、ハードだけではなく、マーケティング概念や経営にも携わるため、うちから提示するフィーは。。。。。
皆、一瞬息が止まります。。。たぶん、相当高いのでしょう…
そして即答する企業はまずいません。
しかし、ここまでうちの話を聞いてくれた企業は「それくらいかかるのは理解できる」と言っていただけます。
そこで、僕自身、例えば「このフィーを払い続けながら弊社と事業を進めて成功できる!イメージが持てますか?」
「御社が弊社に期待するパートはどこですか?自社でできる範囲はどのパート?」など、生意気極まりないですが、弊社と仕事をするイメージを早急に持ってもらい、
できるだけ共同作業で進めていけるよう促します。そうして最終的なフィーを調整します。
弊社が力を入れて支援させて頂いている中小企業にとって、外注費空振りは致命傷です。お金を出すからには成功しないといけませんよね。。。。
デザインフィーに対してどごまで払えるか?払えないか?は、通常クライアント側の判断ですがデザイナーとしてそのフィーがクライアントに取って有効投資か?そうではないか?を判断してあげるのもデザイナーのセンスだと思っています。
ではまた次回!