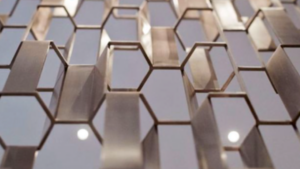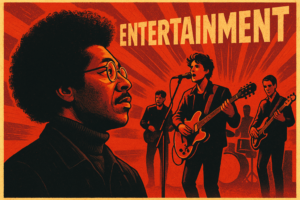おはようございます。関東地域は朝から台風の影響で大雨ですね。本来であれば台風は嫌なものですが、これだけ猛暑が長く続いている中、「おてんとさん」がない日も気持ち的にはホッとします。
昨日ある記事が工業デザイン系、デザイン経営系の方々に取り上げられて賛否両論の意見がSNS上で飛び交っておりました。
僕も執筆させていただいたことのある「ダイヤモンドオンライン」の連載シリーズ「デザイン経営の輪郭」で取り上げられた経産省デザイン政策室 元:室長の佐伯さんの記事です。
https://diamond.jp/articles/-/371062
この記事から、僕が捉えたこと、感じたことを書こうかと。。。
文化醸成思考のデザイナー
この側に立つ人たちは、デザインを「社会や文化を育てる営み」として捉えています。コトづくり重視、パーパスや物語性、共感設計に価値を置き、「利益より文化」「形より体験」と声を大にする。実際、SNSでも「造形に回帰するのは時代遅れ」「社会課題解決こそデザインの使命」という意見が目立ちます。
経済的営利思考のデザイナー
一方で、「デザインは経済の武器だ」と割り切る人たちもいます。彼らにとってデザインとは、国内外市場で勝ち抜くための差別化装置であり、造形美こそ購買意欲を引き出す直接の力です。「形がなければブランドは立たない」「IPとして統合されたデザインこそ収益を生む」という姿勢です。この陣営からは「文化論だけでは飯が食えない」「稼げなければ業界が痩せ細る」という危機感がにじみ出ています。
どちらが正しいのか?
僕の感覚で言えば――どちらも正しい。文化がなければデザインは空虚な商品装飾に堕ちるし、利益がなければ文化を持続させる力を失います。問題は、この二つをつなぐ橋をかけようとしている方々が圧倒的に少ないことです。佐伯さんが強調する「造形の力」も、日本のデザイナーが語る「人間中心の視点」も、両方なくしては未来は描けません。ただし経済市場(国内外)という舞台に立ったとき、本当に必要なのは「文化 × 経済」を両立させるプレイヤーだと思うのです。
僕の結論
今回の記事が投げかけているのは、単なる「デザイン経営の再定義」ではありません。もっと根源的な問いであり、デザイナーは文化を耕す人なのか、利益を生む人なのか?その立ち位置を問われているのだと僕は思います。そして、本当の突破口はその二つを統合できる人材にあります。文化の根を大切にしながら、市場で経済的成果を出す。
そんなデザイナー、そんな経営者が出てこなければ、日本のデザインは「国内の自己満足」に留まってしまうでしょう。
儲ける→成功者として、やはりデザイナー自身が自己実現していくべきだと思うし、僕は20年間儲けもしたし、賠償問題になり負債を抱えたこともあります。市場で経験した「裏切り」を「起こしてはいけない経験」と捉え、デザイナーも経済的寄与をしていかなければならないと感じ、自分の我(経験則からくる思い込み)を捨て、願望(自分の可能性を信じ目指すところ)を強く持ちながら、自分の活動自体が少なからず影響を与えられるよう日々精進しております。w
では、また。