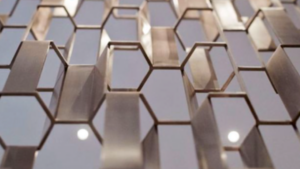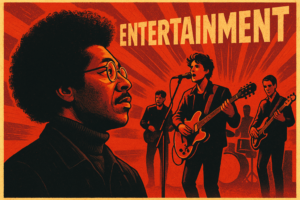みなさん、こんにちは。
ようやく暑さも治り…というか、冬になってきましたね。。。気がつけば10月中ば。。月日が経つのはほんと、早いです。
先日の16日に埼玉県産業技術総合センター(SAITEC)の毎年恒例である「SAITECオープンラボ」で僕が所属している日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)理事長で世界的インダストリアルデザイナーの村田智明さんに「行為のデザイン」から考えるリージョナルデザイン」というテーマでご講演いただきました。
テーマにある「行為のデザイン」ってすごいですね。人間の行動変容や無意識な動作をプロダクトの形状や素材感、技術的な仕組みにより誘導、誘発する問題解決方法ってたぶん、村田さんしかできないのかな。。。と感じました。
ご講演後、久々にゆっくりと村田さんとお話しして、自分が哲学として20年意思を頑なに守ってきたこと、その哲学から起こす行動(事業活動)がそんなに間違っていないことを確認できて嬉しい気持ちとより自信を持てました。
その会話から感じたこと、確信を持てたことを少し話をしますね。
感性と再現の現象
最近の体験ですが、とある小型モビリティのお仕事でしたが、同じ製品がずらっと並べられているシーンを見た時に、何か全ての製品が少しづつ違うんじゃないか?という感覚に陥りました。同じ寸法、同じ材料、同じ素材で作られているのに、何か違和感を感じました。違うと言えば、1つ1つの製品が置かれている位置。。自分が立っている位置と並べられている製品の位置とのズレ。。。その時に「デザインって感性の問題ではなく、再現できる現象じゃないのかな?」と思いました。
ちなみに僕がここで言っている「再現できる現象」とは、結果として得られる「人の感覚的・心理的な反応」や「機能的な効果」が、条件を整えれば誰がやっても同じように得られる状態ってことです。
科学的思考_「何故?」を手放さない姿勢?
インダストリアルデザインの現場には、常に“なぜ”が付きまといます。
・なぜこの形が自然に見えるのか。
・なぜこの構造が安心感を与えるのか。
・なぜこの質感が心地よいと感じるのか。
これらを感覚や経験のみに頼らず、観察と分析を通して掘り下げること。それが、デザインにおける科学的思考です。科学とは、観察し、仮説を立て、検証を重ね、再現性を持って理を見出す営み。デザインも同じく、仮説と検証の連続によって“美しい機能”を探求する行為だと思います。
プロセスで導くびと合理の交点
僕は工業系の人間なので、あえて工業製品に焦点を当てますが、製品をデザインするということは常に条件との対話だと思います。素材の理想と現実、加工の限界、コスト、安全性、環境配慮、企業の様々な問題など。。。
その条件全てが、創造を制約しますが、同時に方向性を与えてくれる「黙示録」でもあるわけです。
観察→仮説→造形→検証→改良
この繰り返しが、美と合理の交点を見つける唯一の方法だと感じます。
完成度の高い製品は、感性のひらめきだけではなくこうした地道な科学的プロセスの積み重ねの上に生まれるものだと思っています。
感性を論理で支えられるということ
科学的であるという姿勢は、感性を否定することではありません。むしろ、感性を支えるための論理を持つことだと思います。
「なぜ、美しいのか?」「なぜ、心地よいのか?」を説明できることです。
・「黄金比(黄金律)」 → なぜ?美しく見えるのか?を「1:1.618」の比率で割合で理解する。
・シンメトリーの法則 → 対象性が持つ視覚的な美を数学的な論理で理解する。
・1/fのゆらぎ → 心地よさを与える規則性、不規則性のバランスによる自然界のゆらぎ現象を数学的に理解する。
上記の例は、感性を科学的に解釈し言葉や計算に置き換えようとした試みです。
感性を科学で語ることは、心や無意識を言葉や数値にすることではなく、それを理解媒体として捉え、関わる全ての方、社会生活へ理解可能とし、それが心の通じる形を再現可能とすることだと感じます。
科学的の上に咲く、美という現象
デザインは科学の延長線上にある。この考え方は、デザインを冷たくするものではなく、むしろ深く温かくします。なぜなら、科学の根底には「人を理解したい」という想いがあるからです。感性という花は、科学という土台の上でこそ咲く。観察と検証を重ね、現象を解き明かしたその先に、“美”は現れる。それは個人の感覚を超えて、多くの人が共感できる美しさとして社会に広がっていくのでしょう。
終わりに。。。
「デザインは科学である」
この言葉の本質は、感性を数式にすることではありません。それは、感性を再現できる形で社会に届けるための知性のこと。科学的思考とプロセスを通して、感性を磨き、再現性を持たせ、社会に機能させる。
その静かな努力の積み重ねこそ、インダストリアルデザインという仕事の美しさだと思います。
以上、「尖がったデザイン」シリーズ第2章でした。w
第3章もお楽しみに!